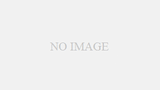脳の神経細胞同士の間には僅かな隙間が
あって、神経伝達物質(ドーパミン、
アセチルコリン等)が行き交うことで
情報のやり取りが行われます。
ドーパミンは、中脳から大脳を繋ぐ
「神経線維」を伝わって大脳下部にある
「線条体」に運ばれて放出されます。
線条体は神経細胞が集まった組織で、
脳の色々な部位と連絡を取り合い、
最適な身体運動が出来る仕組みです。
[ip5_ornament design=”bg-deco-postit4″ width=””]ドーパミンの減少[/ip5_ornament]
ところがパーキンソン病を発症すると、
中脳にある黒質という神経細胞が
減少するため、「ドーパミン」も
減少する傾向が見られます。
そのため、ドーパミンの減少を補う薬を
投与することになるのですが、
初期段階では症状によく効くものの、
長期に亘る服用の結果、日中で薬効が
発揮されない時間帯(オフ状態)には
手足の震えなどが見られ、
逆に薬が効きすぎて(オン状態)
意思に反して手足が勝手に動く
ジスキネジアという症状が見られることが
あります。
[ip5_ornament design=”bg-deco-postit4″ width=””]ウェアリング・オフ 現象[/ip5_ornament]
このように、On、Offの状態が日中に
何度も表れることを
「ウェアリング・オフ 現象」と言います。
薬の作用によって生じる現象ですが、
投薬後、脳内にドーパミンに保存されていて
効果が続いていたのが、パーキンソン病が
進行するにつれて保存しにくくなって
しまうのが原因で、次の薬を服用するまでに
パーキンソン病の症状が表れることになります。
主に利用されるL-ドパ、ドパミンアゴニストの
服用に合わせ、それらの効果を長続きさせる
ために、COMT阻害薬、MAO-B阻害薬、
アデノシンA2A受容体拮抗薬といった薬が
併用されます。
COMT阻害薬、MAO-B阻害薬はL-ドパ、
ドパミンアゴニストの効果を長続き
させる効果が、アデノシンA2A受容体拮抗薬は
ドーパミンとは異なる新しい作用機序によって、
ウェアリング・オフ現象を改善する働きが
あります。
薬が効きすぎる場合に発生するジスキネジアが
見られる場合は、投薬量を減らすなどの対応が
取られます。
[ip5_ornament design=”bg-deco-postit4″ width=””]まとめ[/ip5_ornament]
パーキンソン病治療薬を長期に服用すると、
日中で薬の効果が発揮出来る時間帯、
そうでない時間帯が繰り返される現象が
見られます。
このような現象を「ウェアリング・オフ 現象」と
いいますが、他の薬を併用したり、投薬量を
減らしたりして調整することになります。
主治医に相談して適切に対応することが
望ましいです。